Taste&Seeでは、急性期・回復期・療養型の病院、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の高齢者施設、歯科医院、訪問看護ステーションなど20施設以上へ支援させていただいております。

看護部長
稲垣伊津穂様
月に1回の6回コースでお願いしました。当院は2病棟しかない小さな病院です。口腔嚥下チームとは違う、もっと現場に近い形で歯科衛生士1名、言語聴覚士1名、各病棟より3名の計6名の看護師が参加。新たに「食支援チーム」を立ち上げました。
1回3時間の濃密な研修をして頂きました。毎回、新しい知識や技術を身に付けることで、チームの看護師がキラキラしていき、最後の事例発表内容には私も感動しました。6ヶ月の成長を実感し、本当にコンサルテーションして頂いてよかったと思いました。 今年度もこの新たなチームで、看護師全体に研修をしてもらいます。引き続き、定点的にTaste&Seeさんのフォローアップをお願いしたいと思っています。

オフィスK代表
臼井啓子様
経験値でやっていたトロミのつけ方、食事時の姿勢、食事の形態などを、一から見直す機会になりました。それ以外にも、最初は理由があったものの、いつの間にか漫然と車いすのまま一日を過ごしていただいている利用者さんがいることに気付き、それがどうなのか、という話し合いもできて、以前よりケアの根拠を考えるようになったように思います。また、Taste&Seeさんの助言を得て、学んだことをプレゼンテーションすることもできて、スタッフにとっては良い経験になったのではないでしょうか。正直、弊社のような小さな会社にとって、コンサルティング料は安いものではありません。でもその数倍の価値があったと思います。今後もこの学びが活き続けるように、定期的に見守っていただきたいと思っています。

ベルランド
総合病院
看護部長
前原陽子様
口腔ケアの方法や実践のみならず、食物の匂いや配置などさまざまな工夫のなかで、患者さまの表情が穏やかに変化していくことは、看護職のケアへの動機付けになっています。「食べられないのは仕方ない」・「誤嚥をおこすのは高齢だから」とあきらめや決め付けではなく、患者様の口腔ケアと嚥下訓練を通して「快」のニーズに訴えかけてられるようになってきました。
摂食嚥下ワーキングチームとしての成果発表会も開催しました。患者様個々に応じた嚥下訓練の方法や道具の選択などから、その効果を共有することが出来ました。また、Taste&Seeさんからは、アセスメントからケアの実践までを系統的にご指導いただくことで、「目から鱗」の学びになりました。
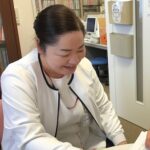
ベルランド
総合病院
副看護部長
畠山知子様
Taste&Seeさんが当院の看護師と一緒に、口腔ケアを実践して頂いた時のことです。脳外科の術後で、傾眠がちな患者様でした。その方に昼食を勧めると「口がすっきりしたから、食べるのがもったいない。」とおっしゃいました。口腔内環境が、患者様のQOLを向上させるのに重要である事を、あらためて気づかせてくれました。
摂食嚥下機能に関する知識,技術の素晴らしさはもちろんですが、患者さんを全人的にとらえ、その患者さんに必要なケアを見出される姿勢に、看護の素晴らしさを伝える大きな役割を担っておられると日々感じています。

きずな歯科医院
歯科衛生士
山口香苗様
私は歯科衛生士ですが、摂食嚥下に携わる際に、まだまだ知識も浅く、どうしても視野が狭くなってしまいがちです。しかし、摂食・嚥下障害看護認定看護師のTaste&Seeさんとお仕事をご一緒して頂く事で、歯科衛生士では思いもよらない視点からの観察や、その他たくさんアドバイスを頂いています。
また自身の知識や歯科医院での摂食嚥下訓練を充実したものにしたいと思い、Taste&Seeさんに毎週勉強会を開いて頂き、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士の資格を得ることができました。これからも訪問先で様々なアセスメントを行い、的確な知識で訓練を実施できるよう、アドバイスを頂きたいと思っております。

フォーリーブス
管理者
堀川勝子様
私は訪問看護師ですが、利用者さんが嚥下訓練をしていくうちに少しづつ食べれるように、飲み込めるようになり喜んでいただいています。 また、職員への教育もしっかりとしていただけ契約してよかったです。「しっかり嚥下訓練が自宅でできます!」と堂々といえるのもTaste&Seeさんのおかげです。

看護部長
星田朋子様
摂食嚥下チームが中心に知識と技術を学んでいます。専門家の介入によって患者様が改善する現場に直面することによって現場の興味が高まっています。また「嚥下マニュアルの作成」や「病院食の形態」に対してもアドバイスを頂いています。これらの活動を続けることでケアのさらなる質向上につながるものと期待しています。

悠人会
介護老人保健施設
サンガーデン府中
元援護部長
河村美枝子様
高齢者が「最後まで口から食べる」ことを支援するために、同系法人の介護施設全6施設の看護管理者に呼びかけ、摂食嚥下ケアの質を高める多職種合同チームを結成し、全施設一斉のコンサルテーション研修の導入を開始しました。
毎回のコンサルテーションでは、私たちはまさに「目からうろこ」の状況でした。アセスメントがいかに重要かわかりました。関わった高齢者が、少しずつ口から食べることができ、栄養状態が改善した例や、誤嚥性肺炎を繰り返していた方が、発熱せず経口摂取できています。また、管理栄養士、言語聴覚士とともに活動することで経口維持加算件数も増加し、経営貢献につながっています。

悠人会
介護老人保健施設
サンガーデン府中
介護課
中川丈士様
どのような状態で嚥下がおこなわれているのか。どこに問題があるのか。どのように観察するのか。どのように対処するのか。今回のコンサルテーションでは、日々関わっている利用者の方を回診していただくことで、摂食嚥下をリアルに学ぶことができました。
何の問題もなく食事が取れていると思っていた方の、口腔内をよく観察することや嚥下時の音を聞くことで、嚥下状態に問題があることを知りました。また、摂食嚥下の5期を意識した介助や観察ができていない現状にも気づかされました。
私たち介護福祉士は、利用者の日々の生活で「食事」というケアに携わることが多い職種です。その中で、いかに安全に食事をたべていただくかが重要となります。摂食嚥下の知識や技術を活かすことで、誤嚥による窒息や肺炎を防ぐことができ、健やかな生活に繋がるケアが提供できるものと考えます。今回の学びを法人内の介護施設で共有し、ケアの定着を図っていきます。

頌徳会
日野病院
現在は大寿会
病院看護部長
(元日野病院)
濱野由美子様
委員会担当の看護師は、毎週の回診で、事例報告をするのは初めてのことだったのではじめは大変そうでした。しかし、途中から学ぶことが楽しみになり、積極的な姿勢に変化しました。これまでの教育では、受け身であり自ら学ぶ姿勢が弱かったのですが、6か月目の事例発表後は、達成感を味わうことにより、外部研修を自ら探して参加するなど、意欲的に変化しました。また、3事例は、学会発表ができ、看護ケアの成果と看護師人材育成の効果が可視化できました。摂食嚥下の知識・技術の獲得がベースとなって、医療・看護の質が向上し、患者様の満足や経営効果に繋がったと思います。

